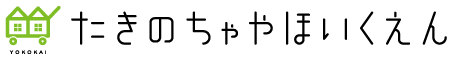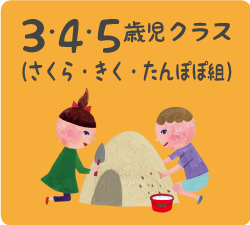
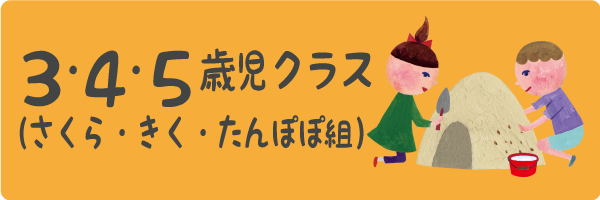
生活の流れが分かり、自分の事は自分で出来るようになります。
保育士や友だちとの関わりが増え、集団で活動することや、一緒に遊ぶ楽しさを知り、仲間関係が芽生えていく時期です。
いろいろな活動を通し、自分の思いを上手に伝えたり相手の思いに気付いたりする中で仲間意識が育ちます。
又、自分で出来ることに喜びを感じ、認められることにより自信をつけ、次の意欲へとつなげていきます。
内面的にも大きく成長し、自分の頭で考えて行動が出来るようになります。集団生活を通じて、きまりを守ることの必要性も分かり、ルールを身に付けます。
就学へ向け、挨拶や健康、自分の意志や意欲を育みます。
子どもが自主的に遊ぶためには、「場所」「時間」「モノ(道具)」が必要です。
又、自分で遊ぶことが、自立・自己の確立となります。
各クラスで自分の食べられる量を盛り付けてもらいます。苦手な物も少しだけ挑戦します。スプーンがしっかり持てるようになれば、お箸に変わります。
食べる時の姿勢や食器の持ち方も身につくようにしています。
 |
 |
幼児期は、一生を通じての食事リズムの基礎をつくる大切な時期です。食に対して関心を持ち、食べる事の大切さを知ってもらえるよう色々なお話しを聞いたり、体験をしています。
この時期に、お腹が空き食べたい意欲を持ち、誰かと一緒に食べると楽しいという経験も知ってもらいたいと思ってます。
又、野菜の栽培や料理の下準備を行うことでより“食”に興味を持ち、健康な身体作りに役立っています。
 |
 |
遊びコーナーは主に4つに分かれています。お世話遊びコーナー、台所コーナー、机上遊びコーナー、構造(積み木)コーナーです。子どもの遊びは、子どもの喜びと自発性、つまり主体性が大切にされたものです。すべての子どもが自分の体験を再現して遊べる環境を用意し、子どもの体験が学びにつながるようにしています。
仲間の中で自分の好きな役を引き受けてその人になりきって遊びます。
様々な感情やふるまい、しぐさの練習ともいえます。この役割遊びが幼児の遊びの中心的なもので、子どもの体験したことの再現だけでなく、社会に適応する態度、習慣、言語を獲得することになります。
 |
 |
構造あそびでは、順次性や数量、位置などの概念を獲得します。友だちとの遊びの中で自分のやりたいことが実現されると満足感と充実感、自己肯定感となっています。
自発的に描いたり、作ったりできるコーナーでは、色々な道具や素材を準備しています。
イメージする力や思考力、判断力を育て、鉛筆やペンの持ち方、ハサミやのりの使い方を学ぶ場となっています。
繰り返し遊ぶことで手の機能が発達するだけでなく、様々な道具を単体あるいは組み合わせることで、より大きなもの、複雑なものへと発展していきます。
 |
 |
 |
 |
ルールを守ることで楽しめる(主にゲーム類)ことがわかり、グループや集団で必要なことを理解し、葛藤や待つこと、譲ることを体験します。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |